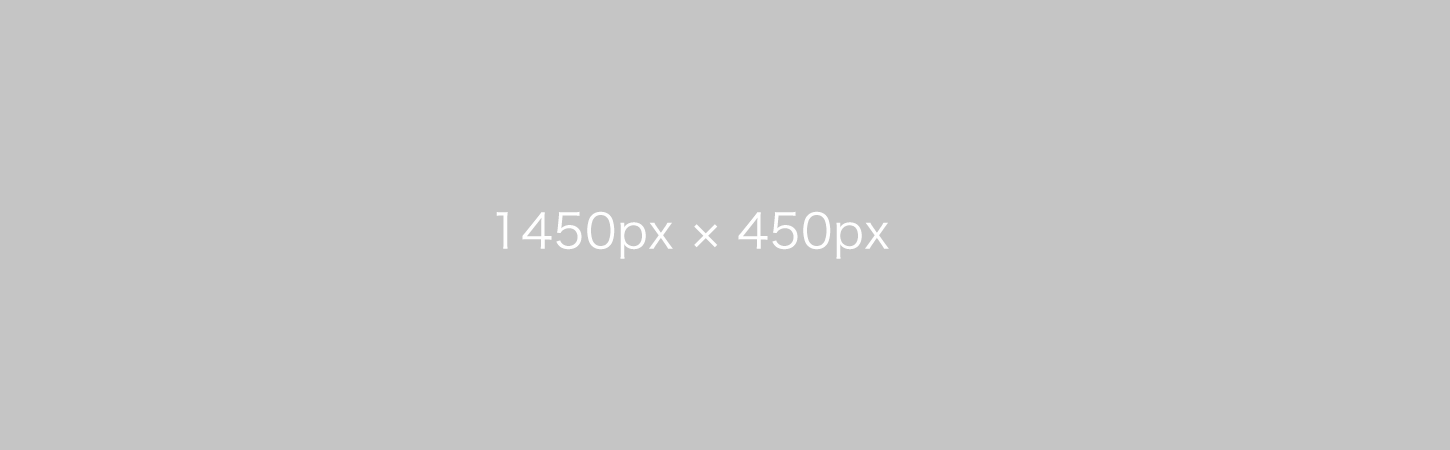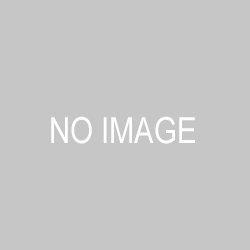風邪
風邪は、誰もが一度は経験するごく身近な病気です。正式には「風邪症候群」と呼ばれ、鼻や喉などの上気道にウイルスが感染することによって起こります。感冒(かんぼう)、急性上気道炎(きゅうせいじょうきどうえん)などともいわれます。
通常は数日から1週間ほどで自然に回復することが多いですが、時に症状が長引いたり、他の病気と見分けがつきにくい場合もあります。
風邪の原因
風邪の原因のほとんどはウイルスによるもので、200種類以上のウイルスが関与しているとされています。ウイルス以外にも細菌が原因となることがあります。代表的なものには「コロナウイルス」「アデノウイルス」「RSウイルス」「インフルエンザウイルス」などがあります。これらのウイルスは、咳やくしゃみなどによる飛沫感染や、ドアノブなどを介した接触感染によって広がります。
ウイルスが原因の風邪は一般的な抗生物質は効果がありません。ただし、ウイルス感染がきっかけで二次的に細菌感染(副鼻腔炎や気管支炎、肺炎など)を起こすこともあり、抗生物質が必要となることがあります。
症状
風邪の症状は感染したウイルスの種類や、個人の体調によっても異なりますが、以下のような症状がよく見られます
のどの痛み、鼻水・鼻づまり、くしゃみ、咳(乾いた咳や痰を伴う咳)、発熱(37〜38℃程度の微熱が多いです)、倦怠感(からだのだるさ)、頭痛や関節痛 などです。
これらの症状は徐々に現れ、数日以内にピークを迎えます。通常は1週間以内に回復しますが、高齢者や小さなお子さま、基礎疾患のある方は重症化するリスクもあるため注意が必要です。
インフルエンザや新型コロナウイルスとの違い
一般的な風邪では対症療法(症状に対する治療のことで咳に対して咳止め、発熱に対して解熱剤の内服など)で自身の免疫力により自然に軽快をしていきますが、ウイルスや細菌感染の中でも迅速抗原検査が可能な「インフルエンザ」「新型コロナウイルス」「溶連菌」の可能性があります。これらが疑われる場合は検査を行い感染の有無の確認を行い、治療方針の決定を行っていきます。
発熱から間もない場合では迅速抗原検査で陰性と結果が出てしまうことがあります。
| 症状・特徴 | 風邪 | インフルエンザ | 新型コロナウイルス | 溶連菌感染症 (咽頭炎) |
|---|---|---|---|---|
| 発症の仕方 | 徐々に始まる | 急な高熱と全身症状 | 緩やかまたは急に出ることも | 急に喉の痛みや発熱が出ることが多い |
| 発熱 | 微熱〜37℃台 | 38〜40℃の高熱が多い | 微熱〜高熱 | 38〜40℃の高熱が多い |
| 喉の痛み | 軽〜中程度 | あり | あり | 非常に強い |
| 咳 | 軽い〜中程度 | 強い(乾いた咳) | 乾いた咳が多い | あまり見られない |
| 倦怠感 | 軽度 | 強い | 中〜強い | あり(だるさ) |
| 筋肉痛・関節痛 | まれ | あり(特に強い) | あり | なし〜軽度 |
| 味覚・嗅覚異常 | まれ | まれ | 比較的よくある | ない |
| 治療法 | 対症療法 | 抗ウイルス薬が有効 | 対症療法・抗ウイルス薬が有効 | 抗生物質が有効 (主にペニシリン系) |
| 感染経路 | 飛沫・接触 | 飛沫・接触 | 飛沫・接触・エアロゾル | 飛沫・接触 |
インフルエンザ、新型コロナウイルは予防接種を行っていても発症をすることがあります。
症状だけで確実に見分けることは難しく、必要に応じて医療機関での検査がおすすめです。
検査
ウイルスや細菌の中でも迅速抗原検査が可能な「インフルエンザ」「新型コロナウイルス」「溶連菌」の可能性があります。これらが疑われる場合は検査を行い感染の有無の確認を行い、治療方針の決定を行っていきます。
検査のタイミング
インフルエンザウイルスおよび新型コロナウイルスの迅速抗原検査を行う適切なタイミングは、ウイルスが増殖をし検出できるウイルス量が存在している必要があります。インフルエンザでは熱が出てから12時間~48時間以内、新型コロナウイルスでは12〜72時間以内に抗原検査を行うと正確な結果が出やすいといわれています。発症後すぐの検査では 検出率が低くなり、症状があっても偽陰性(陰性でも感染している)となることがあります。
肺炎や気管支炎が疑われる場合などでは血液検査や胸部レントゲン検査などが必要に応じて行われます。また症状や治療の経過から、百日咳やマイコプラズマ肺炎などが考えられる際は血液検査での抗体検査を行う場合があります。
症状が長引く際に鑑別が必要な感染症
長引く咳症状がある場合は、風邪症候群後の遷延性咳嗽の可能性もありますが、百日咳やマイコプラズマ肺炎などの感染症が原因となっている場合も考えらえます。また、咽頭通が続く場合ではEBウイルス感染症(伝染性単核球症)の可能性があります。
※テトラサイクリン系抗菌薬は8歳未満の小児に使用すると、歯や骨の発育に影響を与える可能性があるため、使用が避けられることが多いです。
百日咳
百日咳は、ボルデテラ・パータシス(Bordetella pertussis)という細菌による呼吸器感染症です。激しい咳が数週間〜数か月続くのが特徴で、特に乳児では重症化しやすく命に関わることもあるため注意が必要です。名前の「百日」は、咳が長期間続くことに由来します。ワクチンもあり、4種混合ワクチンを幼児期に接種を行いますが、5~10年程で抗体価が低下するため、成人でも感染します。学童期(5~6歳)や妊娠後期での任意追加接種が推奨されています。主な感染経路は飛沫感染と接触感染になります。
百日咳は2週間以上の遷延性、発作性咳嗽、吸気性笛様音、夜間悪化などの症状によりその感染を疑われますが、成人での感染では症状が非特異的ではっきりせず、発作性の咳を示さないことも多く、病歴や家族歴など周囲の感染状況が重要となります。
感染後はカタル期(1〜2週間)といわれる風邪に似た症状(鼻水、くしゃみ、軽い咳、微熱など)を呈し、次第に咳症状が強くなっていきます。その後、痙咳期「けいがいき」(2~3週間)といわれる、夜間に起こりやすい発作性けいれん性の咳が出現します。その後、回復期となり徐々に激しい発作性の咳は落ち着いていき2~3週間程で回復していきます。
検査
百日咳の診断には、培養法、LAMP法、血液検査が主な方法となります。
LAMP法は百日咳菌毒素遺伝子を検出するための高感度な検査方法です。血液検査同様外部へ検査を委託することが多く、結果が出るまで時間を要します。後鼻腔ぬぐい液での検査となります。
培養法は鼻咽頭の分泌物を特殊な培地で培養を行い百日咳の検出を行います。百日咳菌抗体半定量
血液検査では血中の百日咳菌-IgM抗体と百日咳菌-IgA抗体を測定することで感染の確認を行います。IgAもしくはIgM抗体が11.5NTU以上の場合は陽性と診断されます。
IgMおよびIgAのいずれも陰性時は百日咳菌-IgG抗体の検査を行います。IgG抗体価が100EU/ml以上時は百日咳と診断を行います。IgG抗体価が10~99EU/ml時はワクチン接種歴の確認を行い、接種歴がない場合は陽性、接種歴があるもしくは不明の場合ではペア血清で2倍以上上昇していれば陽性と診断をします。10EU/ml未満時は発症してから4週間以上経過をしていれば陰性、4週間未満でペア血清で10EU/ml以上に上昇をしていれば陽性と診断をします。
治療
クラリスロマイシン 200mg 1日2回 1回1錠 7 日間
アジスロマイシン 500mg 1日1回 1回1錠 3~5 日間
といったマクロライド系が第一選択薬として使用されることが多いですが耐性菌も出現するようになり、耐性時はST合剤が使用されます。ニューキノロン系抗生物質(レボフロキサシンなど)、テトラサイクリン系(ビブラマイシンなど)も感受性があるため使用されます。
マイコプラズマ感染症
マイコプラズマは若年者に多く見られる感染症です。呼吸器系に感染することで、急性咽頭炎(いわゆる風邪)、気管支炎、肺炎と様々な症状を引き起こすことがあります。マイコプラズマは細胞壁を持たない細菌のため、溶連菌感染などで使用される、ペニシリン系やセフェム系の抗生物質が全く効きません。マイコプラズマに感染をしたからといって必ず抗生物質を飲まないと治らないというわけではなく、自然に治癒することも多いです(特に咽頭炎や気管支炎)。肺炎や症状が強い場合ではまれに髄膜炎や脳炎といった重篤な合併症を起こすことがあるため、抗生物質での治療を行います。
マイコプラズマは感染を起こしてから2〜3週間で発症をします(潜伏期間)。最初の症状は咽頭痛や発熱で、数日後から乾いた咳の症状が起こり、次第に痰が絡むようになっていき、解熱後も数週間程長引くことがあります。
検査
マイコプラズマ感染症の診断には、迅速抗原検査、LAMP法、血液検査が主な方法となります。
迅速抗原検査は咽頭のぬぐい液を使用し検査を行いますが、マイコプラズマ肺炎時ではマイコプラズマは主に下気道で増殖をするため、上気道である咽頭の検体では十分な菌が存在せず、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症のように感度が高くないため、陰性の結果でも感染していることがあります。また、肺炎を起こしていても胸部聴診上はっきりとしないことがあります。
血液検査では血中のマイコプラズマ抗体(IgM:マイコプラズマ抗体半定量 PA法)を測定することで感染の確認を行います。PA法はIgMを検出する検査方法で、IgM抗体は感染後1週間程度で上昇し、2~6週間程でピークとなります。単一血清もしくはペア血清で診断を行います。単一血清では抗体価が320倍以上。ペア血清では感染初期の(急性期の)血清と、症状が改善してきた回復期の血清の2回採取を行い、それぞれの抗体価を測定します。抗体価が4倍以上に上昇していれば、感染と診断ができます。
LAMP法はマイコプラズマ菌の遺伝子を検出するための高感度な検査方法です。血液検査同様外部へ検査を委託することが多く、結果が出るまで時間を要します。咽頭ぬぐい液または喀痰での検査となります。
治療
抗生物質の内服薬での治療となります。
クラリスロマイシン 200mg 1日2回 1回1錠 10 日間
アジスロマイシン 500mg 1日1回 1回1錠 3 日間
レボフロキサシン 500mg 1日1回 1回1錠 7 日間
ドキシサイクリン 100㎎ 1日1~2回 1回1錠 7~14 日間
などの抗生物質での治療となります。
伝染性単核球症
長引く(2~3週間)咽頭痛や発熱の際はEBウイルス感染が原因となる伝染性単核球症の可能性があります。
EBウイルス感染は成人までに90%~ほぼ100%の人が感染するといわれているほど一般的な病気です。主に唾液を介して感染をし、小児期の感染では無症状もしくは軽い風邪程度の症状のことが多いですが、若年成人(20~30歳前後)での感染では強い症状が出現します。症状は4~6週間の長い潜伏期間後、発熱、咽頭扁桃炎、リンパ節腫脹、異型リンパ球増加、肝機能異常、肝脾腫などの症状が出現します。
咽頭扁桃炎のため、扁桃腺が赤く腫れ、白苔が付着しているため、溶連菌感染症との鑑別が必要となります。溶連菌の迅速抗原検査を行い、結果が陰性時に偽陰性と考えてペニシリン系抗生物質の内服を開始すると皮疹が出現してしまうことがあります。
症状が強く、場合は血液検査によりグロブリンクラス別ウイルス抗体価(IgM型EBウイルス抗体) および血算やCRP(炎症反応)、肝機能などの評価を行います。
EBウイルス感染症と診断された際は抗ウイルス薬はないため、解熱鎮痛剤などでの対症療法となります。高熱と強い咽頭痛から飲食ができずに脱水となることがあるため、必要があれば点滴での補液が必要となります。
治療
つらい症状に合わせた、症状を緩和する薬の処方となるため、診察時に困っている症状を伝えることで薬の内容が変わります。ウイルスが原因の風邪には抗生物質が効かないため、ウイルス感染が疑われる場合には抗生物質の処方は行われません。
検査の結果、溶連菌感染と診断された場合は抗生物質の処方、インフルエンザや新型コロナウイルスと診断された場合は必要に応じて抗ウイルス薬の処方が行われます。