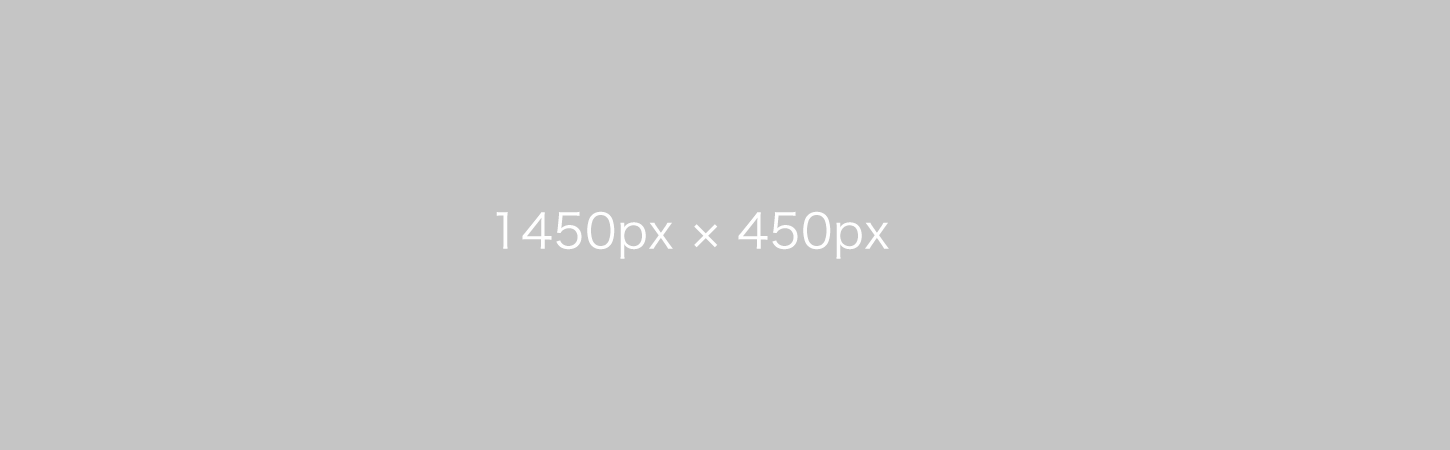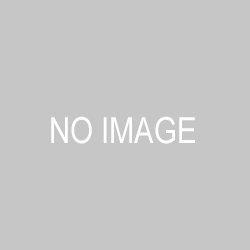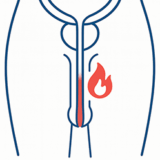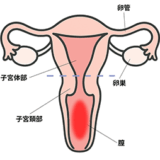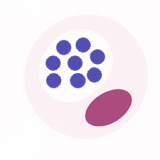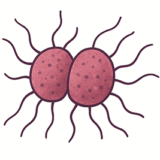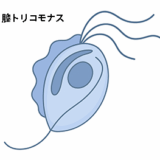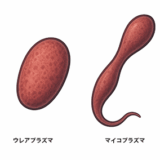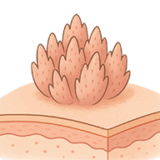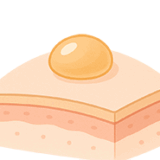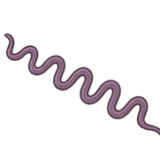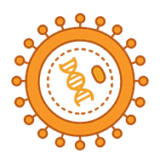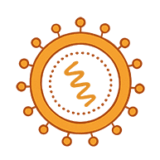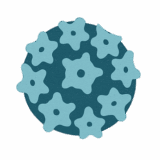C型肝炎
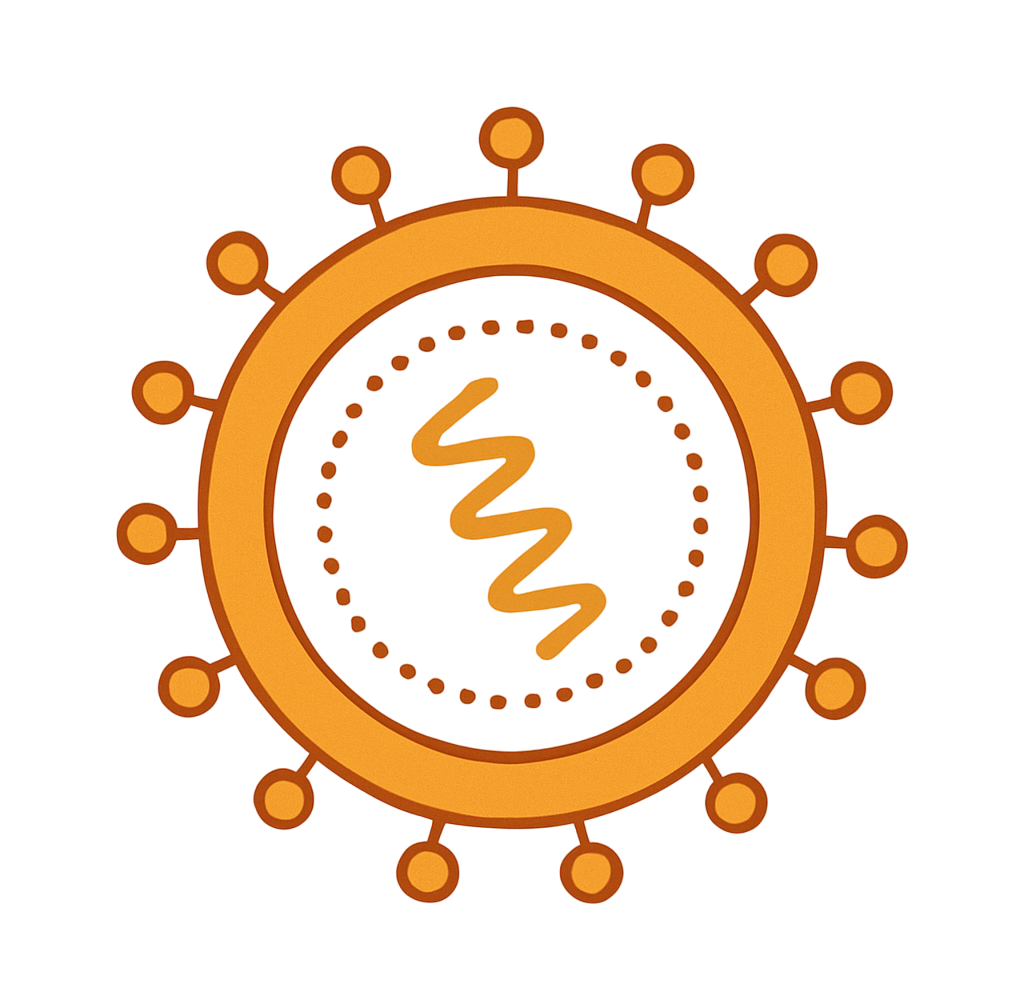
C型肝炎はC型肝炎ウイルスが血液を介して感染をします。B型肝炎に比べると感染性は低いですが、通常の感染で60~70%が慢性化するといわれ、高い慢性化率が問題となっています。感染をして2~14週間の潜伏期間を経て急性肝炎を起こすことがありますが、急性肝炎を起こすことはまれで症状のない不顕性感染のことが多いです。感染をしてから約30~40%の人は自然に治癒し、ウイルス量が減少していき次に抗体価が減少していきます。残りの約60~70%の人はキャリア化し、長期にわたってウイルスと抗体が検出されることになります。
キャリアの状態は肝炎などを発症している状態ではなく、体の免疫力の低下など何かをきっかけにして、ウイルスが増殖しC型肝炎を発症し「肝炎」を発症させる可能性があります。一方で、キャリアのまま何もなく一生を過ごすこともあります。肝炎が慢性化し長い期間続くことを慢性肝炎といい、慢性肝炎が続くと肝臓の細胞が破壊され、炎症により肝臓が線維化することで、「肝硬変」といわれる肝機能が著しく低下した状態になっていきます。慢性肝炎のうち30~40%で約20年の経過で肝硬変へと進行をしていきます。
B型肝炎と異なり感染を予防するためのワクチンはありません。
原因
C型可肝炎ウイルス(HCV)が血液を介して感染をします。感染経路としては、輸血や注射器の使い回し、針の使いまわしをした入れ墨などが挙げられています。
感染経路
C型肝炎ウイルス感染者の血液を介して感染をします。感染確率の高いものとしては、注射器や針などの使いまわし、不衛生な出血を伴う医療・民間療法。感染率は低いですが母子感染や性行為での感染も起こりえます。
性行為での感染は傷口がある場合や、生理中など出血がある場合は感染のリスクが高くなります。通常のキスでは感染はほぼないと考えられていますが(唾液では感染を起こしません)、唇や歯茎からの出血がある場合は感染の可能性があります。
潜伏期間
感染から症状が出るまで2~14週間
症状
HCV感染後2~14週間の潜伏期間後に急性肝炎を起こすことがあるがまれで、多くは症状をのない「不顕性感染」となります。感染後60~70%が慢性肝炎となるといわれています。慢性肝炎中はほぼ無症状で経過をし、30~40%で約20年の経過で肝硬変へと進行し、食道静脈瘤の合併や黄疸、腹水貯留、意識障害などを起こし死に至る危険性があります。
検査可能時期
感染機会から、HCV抗体検査は3.3カ月。もしくは、HCV-RNA検査は6~9日で個別、さらに2日で50プールが検出できるようになるため、検査方法によりますが11日経過していれば可能です。
検査方法
採血を行い血液検査で感染の有無の判断を行います。
HCV抗体検査(感染機会から3.3か月後から検査可能)
一般的なC型肝炎の検査はスクリーニングとしてHCV抗体検査を行います。HCV抗体は「現在感染している人」「過去に感染をしたことがある人」で陽性となり、感染初期(感染機会から3.3カ月内)ではHCV抗体は陽性化しないウインドウ期になるため、感染機会から3か月経過して検査が可能となります。HCV抗体測定のみで C型肝炎の診断をつけることはできません。
HCV-RNA定量検査(感染機会から11日後から検査可能)
HCV抗体をスクリーニング検査として実施し、HCV抗体が陽性の場合は現在の感染の有無を調べるために、HCV-RNA定量検査を行います。HCV-RNA定量検査は6~9日で個別の核酸増幅検査が可能となり、さらに2日経過し、50プールの核酸増幅検査で検出できるようになるため、10日のウィンドウ期があります。
検査費用
自費診療ではクリニックにより検査費用が異なります。
治療法
C型肝炎の治療は専門の医療機関で行われます。
治療はインターフェロンを使用した治療と、インターフェロンフリーの治療、ウイルス除去が困難な方での肝庇護療法となります。
参照
血液製剤等に係る遡及調査ガイドラインQ&A https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/dl/120319-03.pdf
厚生労働省 血液製剤の安全対策について https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000198245.pdf