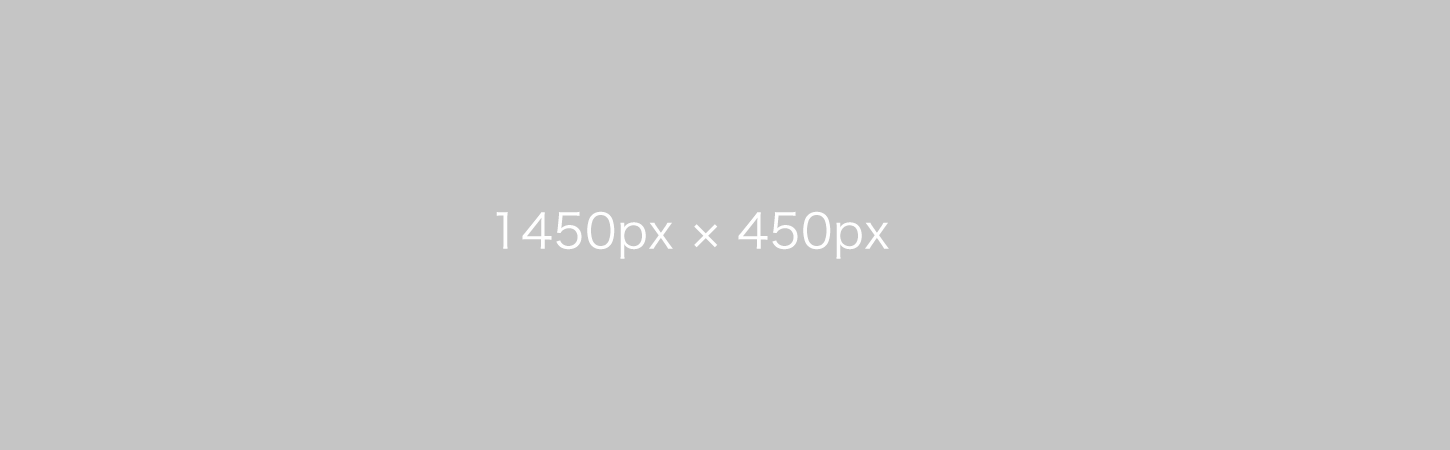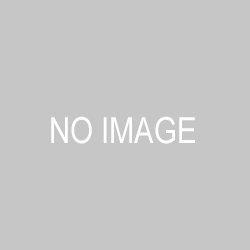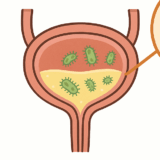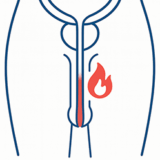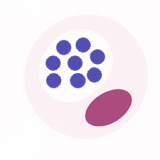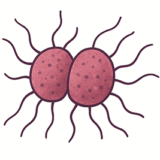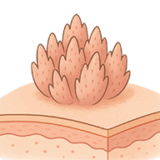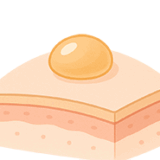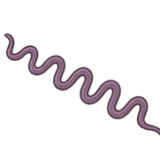排尿時痛
排尿時痛とは、おしっこをする際に痛みやしみるような感覚、不快感を感じる症状です。男女ともにみられる症状ですが、原因はさまざまで、適切な診断と治療が必要です。
女性での頻尿と排尿時痛の症状がある際は膀胱炎のことが多いといわれていますが、性感染症との鑑別が必要となることがあります。男性の排尿時痛では、前立腺炎や尿道炎が原因となることが多く、精液や会陰部の症状にも注意が必要となります。急性前立腺炎は敗血症のリスクがあるため、迅速な診断と抗菌薬治療が必要となります。
主な原因
排尿時痛は、以下のような疾患や状態が原因で起こることがあります。
尿路感染症
膀胱炎
尿の終わりの頃に痛みが出現します。女性に多く、頻尿・残尿感・下腹部の不快感を伴うことが一般的です。膀胱から腎盂に上行感染をすると腎盂腎炎となり、発熱や背中の痛みを伴うようになることがあります。
腎盂腎炎
発熱や背中の痛み(腰痛)を伴うことがあり、膀胱炎よりも重症の状態となります。
尿道炎
尿の出はじめにひりひりとした痛みや違和感が出て、主に男性で症状が出現します。尿道は男性の方が長いため、女性では尿道炎をおこしていても膀胱炎を合併して尿道炎のみの症状がわかりにくい場合や、性感染症では子宮頚管炎による症状が出るため、男性ではっきりとした症状が出ることが多いと考えられています。原因はクラミジアや淋菌などの性感染症が代表的で、性感染症以外では大腸菌などの一般細菌によって起こります。
前立腺炎(男性)
尿の出はじめに痛みが出現します。前立腺が炎症を起こし、痛みや排尿困難などの症状を起こすことがあります。原因は、尿道から侵入した大腸菌などの菌や、淋菌・クラミジアなど性感染症に関する菌が感染することによっておこる急性細菌性前立腺炎、急性炎症が治りきらずに菌が前立腺に残り炎症を慢性的に起こす慢性細菌性前立腺炎、細菌は検出されませんが、前立腺や骨盤神経の慢性炎症・過敏状態が関与するといわれる慢性前立腺炎(慢性骨盤痛症候群)があります。
急性細菌性前立腺炎では発熱、排尿時痛、頻尿、排尿困難、会陰部(肛門と陰嚢の間)の痛みが主な症状になります。慢性前立腺炎(慢性骨盤痛症候群)では、残尿感、頻尿、排尿時痛、射精前後の痛み、会陰部の不快感などの症状になります。
結石(尿路結石)
尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に結石ができてしまい、結石が詰まることで症状が出現します。尿管に結石がある状態を「尿管結石」といいますが、尿管結石が尿管を刺激し攣縮(けいしゅく)をおこすことで、尿管が収縮し尿が流れなくなり腎盂~尿管で尿がたまり内圧が上昇することで痛覚のある腎臓で強い痛みを腰背部などで起こします。結石が膀胱まで落ちきると、強い痛みはなくなり膀胱炎のような症状が膀胱を結石が刺激することで起こります。尿道までくると、排尿時に結石が尿道を刺激するため尿を出すときに痛みが生じ、詰まってしまうと排尿困難となることがあります。
尿管結石は水腎症や膀胱炎、腎盂腎炎の原因となることがあります。排尿痛以外の症状では多くは血尿を認めます。
性感染症
クラミジア感染症、淋菌感染症、性器ヘルペスなどにより、排尿時痛や違和感が生じます。特に、ヘルペス性尿道炎や淋菌性尿道炎(男性)では強い痛みが生じます。
外陰炎・膣炎(女性)
尿が炎症を起こした外陰部や膣口に触れることによって起こる“接触痛が主な痛みの原因となります。しみるような痛み(ヒリヒリ感、灼熱感)で「尿が触れるとしみる」と表現され、排尿のはじめに痛みがでます。膀胱炎では排尿の終わりごろに痛みが出るのが特徴のため痛みの出るタイミングに違いがあります。
細菌性膣症、カンジダ膣炎、トリコモナス膣炎などが原因となります。
間質性膀胱炎(膀胱痛症候群)
感染がないにもかかわらず、膀胱に痛みや不快感が続く疾患です。尿意が頻繁で、排尿後もすっきりしないと感じることがあります。
膀胱がん、前立腺がん
前立腺がんは早期ではほとんど症状がありませんが、進行することで、尿や精液に血が混じる、排尿困難、排尿時痛などの症状が出現します。
膀胱がんは早期では無症候性肉眼的血尿といわれる、痛みなど他の症状のない血尿があります。血尿に気づき、すぐ泌尿器科を受診した際は早期の場合が多いです。信仰することで、頻尿、排尿時痛、残尿感などの膀胱炎のような膀胱刺激症状が出現するようになりますが、これは膀胱がんが膀胱の深層に進行することによる症状となります。
放置するとどうなる?
排尿時痛の原因が感染症の場合、放置すると腎盂腎炎などの重篤な合併症につながることもあります。また、性感染症を見逃すとパートナーへの感染や将来的な不妊症のリスクもあります。
検査
排尿時痛がある際は以下の検査を行い、鑑別を行います。
尿検査(尿定性検査、尿沈渣、尿培養):いわゆる尿検査になります。中間尿といわれる、出はじめの尿ではなく排尿途中の尿を検査をすることで膀胱炎の検査を行うことができます。尿道炎が疑われる場合では初尿(出はじめの尿)での検査を行います。男性の性感染症の検査は尿検査で行います。
性感染症検査:男性では初尿、女性では膣ぬぐい液での検査を行います。
血液検査(炎症反応、腎機能):発熱を呈している場合(急性前立腺炎、腎盂腎炎、精巣上体炎など)では、血液検査を実施し、白血球数やCRP、腎機能などの評価を行います。
超音波検査、腹部CT検査:尿路結石(腎結石、尿管結石など)や尿路閉塞がないかを調べます。結石が原因となる腎盂腎炎ではなかなか治らないことがあります。また、腫瘍(膀胱がんなど)の評価にも用いられます。
レントゲン検査(KUB):小さい結石(2mm以下)だとレントゲン検査でわからないことがあります。カルシウムを含んだ尿路結石がどこにあるかをレントゲンで評価を行います。
膀胱鏡検査:腫瘍や間質性膀胱炎が疑われる際に実施されます。
当院では、専門的な検査機器がないため、「尿検査、血液検査」を行います。
前立腺がんや前立腺肥大症、膀胱がん、尿路結石の詳細な評価は専用の機器が必要となり、当院では診察を行うことができませんのでご了承ください。
治療
排尿時痛の原因により治療方法は大きく異なります。細菌感染が原因で症状が起きている場合には、必要に応じて尿検査を実施し、抗生物質での治療を行います。多くは、内服をはじめて数日で症状は良くなりますが、耐性菌や結石が原因の場合などではなかなか改善せず、抗生物質の変更は他の検査が必要となることがあります。症状が改善しても、内服を止めずに処方通りのみ切ることが再発を防ぐために大事になります。
性感染症が原因となる場合では、パートナーも感染をしている可能性が高いため、パートナーと一緒に検査と治療を行う必要があります。