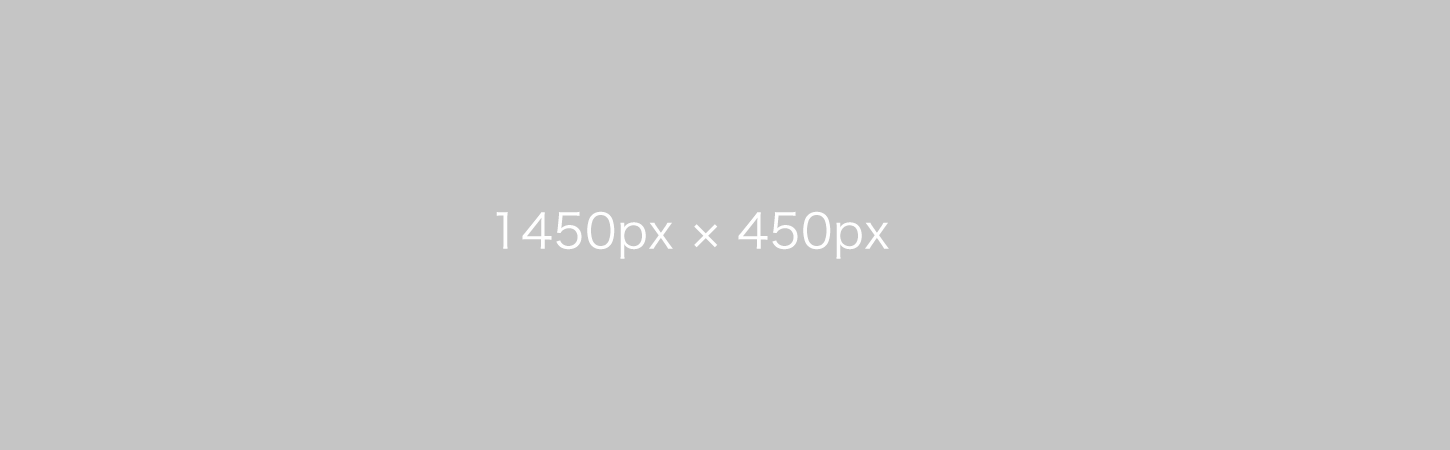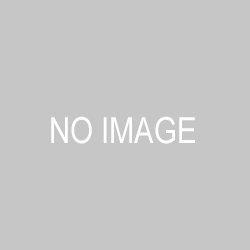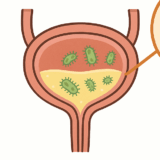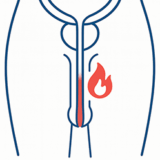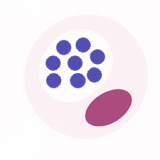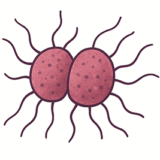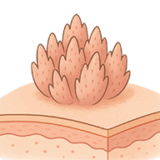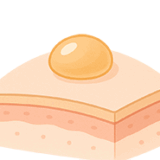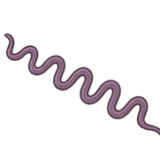梅毒
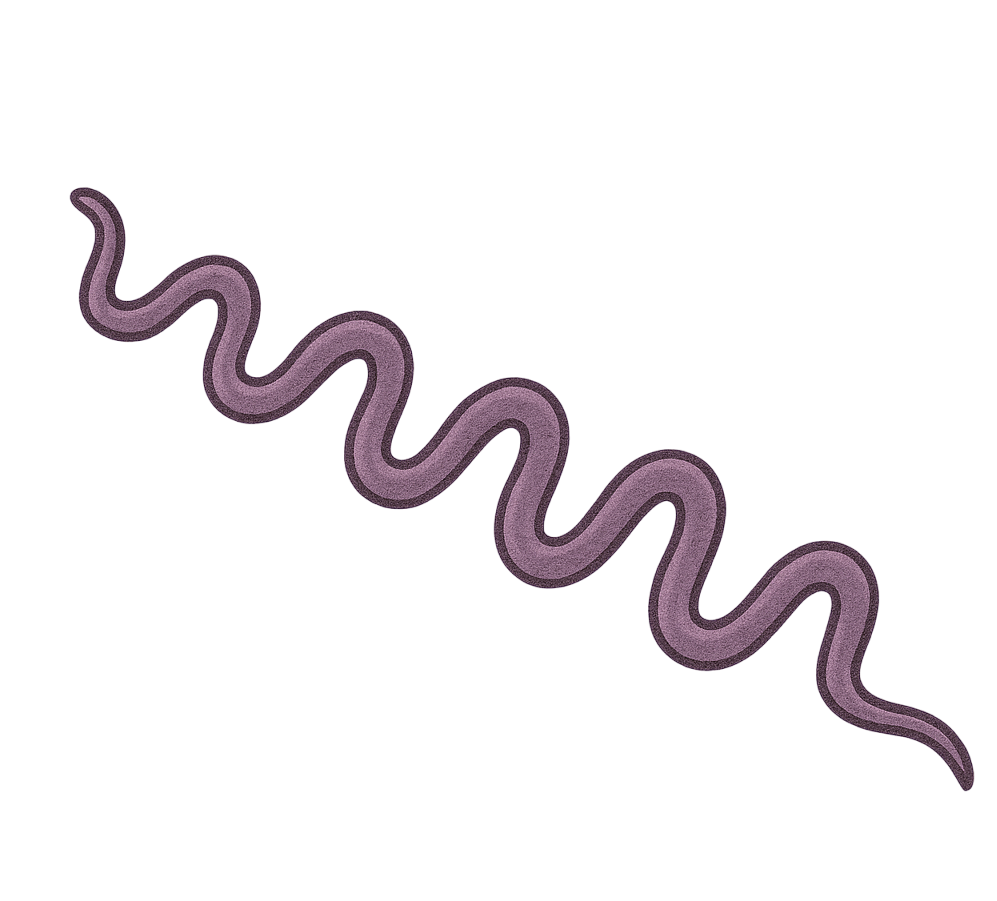
トレポネーマという細菌に感染することで発症します。ペニシリンが発見される以前は、多彩な症状が出現し死に至る、不治の病として恐れられていました。現在は検査、治療が進歩し多くは1,2期での早期発見と治療が可能となり、3,4期の梅毒はほとんどみられなくなりました。近年急激に感染者数が増えており、感染報告者数は淋菌感染症を上回り性感染症ではクラミジアに次ぐ2番目に多い性感染症です。
梅毒の感染は予防接種はありませんが、感染が疑われる機会から72時間以内に内服をするドキシペップで梅毒の87%感染を防ぐことができます。
男性では20~40代、女性では20代の感染報告が多いです。原因ははっきりとわかっていませんが、SNSやマッチングアプリなどを通じた不特定多数の相手と性交渉の機会が増えたことが原因の1つと考えられています。
梅毒の検査は直接細菌を検出する検査を行うことができないため、梅毒に対する「抗体」で検査を行います。感染機会からRPR抗体:2~4週間、TP抗体:4~6週間経過した後陽性となるといわれていますが、個人差が大きいため確実な陰性の診断のためには感染機会から3カ月経過してからの検査が必要となります。
原因
梅毒トレポネーマが粘膜や微細な傷のある皮膚に侵入をし、感染することで発症をします。
感染経路
梅毒トレポネーマという細菌を含む体液(精液、唾液、肛門分泌物、血液、しこりや硬性下疳の浸出液など)が「粘膜や微細な傷の皮膚に接触すること」で感染を主な感染経路は性行為となります。1回の性交渉での感染率は15~30%と高く、感染力は強いです。
- 性交(膣性交・アナルセックス・オーラルセックス)
- 性的な粘膜接触(性器と性器、性器と口、性器と肛門など)
- 性交類似行為(素股など)でも粘膜が触れ合えば感染の可能性があります
- キス(ディープキスで感染する可能性があります、唇を軽く触れる程度のフレンチ・キスでは感染の可能性は低いといわれています)
梅毒トレポネーマは熱や乾燥に弱く、体外ではすぐに死滅するため、以下のようなことではまず感染しません。
- 浴槽の共用、温泉、プール、シャワー
- トイレの便座やウォシュレットの水流
- コップや箸の使いまわし
極めてまれには、傷のある手指が多量の排出菌に汚染された物品に接触して伝播されたとする報告もある。と国立健康危機管理研究機構のHPに記載があるため、日常生活の感染は0とはいいきれません。
梅毒は感染者の粘膜や皮膚の病変部に菌が大量に存在しするため、粘膜同士の接触や微細な傷への接触することで感染を起こします。
潜伏期間
感染機会から症状が出るまで3~6週間
症状
感染時期や症状、部位により下記のように分類されます。
梅毒の分類
早期梅毒:感染から1年未満をいいます。早期梅毒のうち1期を「感染から1週~3か月」、2期を「感染から1か月~1年を2期」に分類します。
後期梅毒:感染から1年以上を後期梅毒(3期)に分類します。
潜伏梅毒:梅毒血清反応陽性でも症状ない状態。梅毒1期と2期の間、2期の症状消失後を主にさし、感染後1年以内を早期潜伏梅毒、感染後1年以降を後期潜伏梅毒に分類します。
神経梅毒:梅毒トレポネーマが中枢神経系に感染した状態で、どの病期でも起こりえます。
感染をすると血行性に全身に広がり、全身性の慢性的に進行する感染症です。時間経過とともに症状が進行し最終的には大動脈瘤や脊髄癆といった心血管系、中枢神経系に影響し日常生活が困難となり死に至る可能性のある感染症です。
1期(早期梅毒のうち、感染から1週~3か月)
感染から3週間程で梅毒トレポネーマが感染した部位(陰部や唇、口の中、肛門、傷口の周りなど)に、初期硬結、硬性下疳などの病変が出現します。リンパ節の腫れが出現することもあります(性器感染で鼠径部の腫れなど)。治療をしなくても3~6週間で自然に治っていきます。
1期では症状が出ていても、検査では感染から早すぎるため、TP抗体、RPR抗体ともに陰性と出てしまう「偽陰性」の場合があります。医師の診察により、「感染機会があり、症状から梅毒の可能性が高いと判断した場合、治療を開始し、治療開始の2~4週間後に、TP抗体、RPR抗体の再検査を行い、陽性時は活動性梅毒と診断をします。また、症状がはっきりとしないものの疑わしい場合では、2~4週間の期間を開けてTP抗体、RPR抗体の再検査を行い診断を行います。
初期硬結(しょきこうけつ):感染部位の皮膚や粘膜にできるしこりのことをいいます。赤く腫れたような見た目で、痛みやかゆみはありません。男性は冠状溝や亀頭陰茎性器周辺の皮膚、女性は膣内、大陰唇・小陰唇周辺の皮膚、 口腔・咽頭の粘膜などにできます。
硬性下疳(こうせいげかん):初期硬結が破裂し潰瘍となった状態のことをいいます。痛みはないため、気づかずに放置してしまうことが多いです。病変部には病原菌が大量に存在するため、パートナーへと感染をさせてしまう可能性が高いです。硬性下疳は治療をしなくても1~3か月で治ります。鼠径部のリンパ節が無痛性に固く腫れる無痛性横痃も出現することがありますが自然に治ります。
2期(早期梅毒のうち、感染から1か月~1年)
治療をしないまま放置をすると梅毒が進行し、菌が全身に広がることで、全身に様々な症状が出現します。特徴的な症状として、「バラ疹」があり、手のひらや手背、前腕、下腿、体幹などを中心に全身に赤い無痛性の紅斑が出現します。その他の皮膚粘膜症状としては丘疹性梅毒疹(エンドウ豆程の赤褐色の丘疹や体幹、顔面、四肢、足底、手掌に出現)、扁平コンジローマ(肛門や外陰部に薄い紅色から灰白色の分泌物を伴ういぼ)などを認めます。
治療をしなくても自然に消失していきますが、抗生物質での治療をしない限り梅毒トレポネーマは体内に残ったままのため進行し、再発と寛解を繰り返し3期へ移行をしていきます。
3期(感染から1年~。いわゆる後期梅毒)
抗生物質での治療をせずに感染後1年~数十年が経過すると、皮膚・骨・筋肉・肝臓・腎臓など全身に固いしこりやゴムのような腫れ「ゴム種」という腫瘍ができます。鼻骨周辺に形成するものを鞍鼻といいます。
大動脈瘤や大動脈弁逆流症といった心血管梅毒、脊髄癆や進行性麻痺などの晩期神経梅毒も合併し、死亡に至ります。近年では抗生物質の治療により3期梅毒は稀といわれています。
活動性梅毒と診断した場合は HIV 抗原抗体検査を保険適用で検査が可能なため、検査を行う場合があります。
検査可能時期
感染機会からRPR抗体:2~4週間、TP抗体:4~6週間経過した後陽性となるといわれています。個人差が大きいため確実な診断は感染機会から3カ月経過したタイミングでの検査が必要となります。
検査方法
採血による血液検査で感染の有無を確認します。梅毒トレポネーマ抗体(TPHA)、STS(RPR)の定性検査を行います。検査の結果、梅毒の感染を認めれば定量法での検査を行い、治療を開始していきます。RPRの定量法は治療効果の判定に用いられ、治療前の数値を基準にし判断していきます。治癒効果の判定にはRPRの定量検査を1か月毎に行っていきます。
定性検査は(+)、(-)で結果が表示され、定量検査は数値で結果が出ます。定性検査は抗体の有無を判定するため、梅毒感染の有無をスクリーニングする目的で検査されます。定量検査は抗体の量を数値で測定するため、治療効果の判定に用いられます。
検査結果の見方
| RPRの結果 | TPHAの結果 | 結果の解釈 |
| RPR(+) | TPHA(+) | 梅毒に感染しています |
| RPR(+) | TPHA(ー) | 初期の感染の可能性 生物学的偽陽性 |
| RPR(ー) | TPHA(+) | 梅毒治療後で感染していない 梅毒治療後で感染しているが検査時期が早すぎる |
| RPR(ー) | TPHA(ー) | 梅毒に感染していない 感染しているが検査時期が早すぎる |
1期では症状が出ていても、検査では感染から早すぎるため、TP抗体、RPR抗体ともに陰性と出てしまう「偽陰性」の場合があります。医師の診察により、「感染機会があり、症状から梅毒の可能性が高いと判断した場合、治療を開始し、治療開始の2~4週間後に、TP抗体、RPR抗体の再検査を行い、陽性時は活動性梅毒と診断をします。また、症状がはっきりとしないものの疑わしい場合では、2~4週間の期間を開けてTP抗体、RPR抗体の再検査を行い診断を行います。
TPHA:過去に1度でも梅毒に感染すると生涯にわたって陽性となります。TPHAは感染機会から8週間後に陽性となるため、検査時期が早いと陰性と結果がでることがあります。
RPR:感染から3~4週間ほどで陽性となります。自己免疫疾患などで陽性と出てしまう「生物学的偽陽性」となることがあります。定量法では梅毒の治療効果の判定にも用いられますが、定性法でも治療後しばらくは陽性が続きますが、しばらくすると陰性化します。
手術の前の術前感染症検査や保健所での無料匿名検査で感染が判明することもあります。
検査費用
初診料・検査費用等で3割負担の場合、自己負担額は2000円台となります。
治療法
抗生物質の内服治療もしくは筋注になります。
抗生物質
第1選択薬
以下の治療が基本となります。
アモキシシリン(サワシリン)250mg 1 回 2錠 1日3回 28日間 内服
※治療開始の24時間以内に発熱など(ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応)と開始から8日目頃から 起こりうる薬疹があり、女性に多いといわれています。
ベンジルペニシリンベンザチン(ステルレイズ) 240万単位 単回 臀部筋肉内注射
後期梅毒(感染から 1 年以上経過している場合)では 1 週ごとに計 3 回筋注
※筋注の数時間後にヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応が起こることがあります。
第2選択薬
ミノサイクリン 100mg 1回1錠 1日2回 28日間 内服
ペニシリン系にアレルギーがある場合や妊娠中、神経梅毒の合併がある際は専門の医療機関での治療が必要となります。
抗生物質の内服の場合は、1日3回で4週間(治療の経過ではさらに必要)の内服が必要となり、飲み忘れがあると治療効果が得られなくなる可能性があります。
治療開始後24時間以内に発熱、頭痛、皮疹などの「ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応」が出現することが10~35%であるといわれており、女性に多いといわれています。抗生物質により病原となる細菌が大量に破壊され、細菌の毒素が血液中に放出されることが原因と考えられています。この反応は24時間以内に落ち着きます。抗生物質開始後1-4時間で症状が出現することが多いです。
治療効果の確認
治療開始後、 4 週ごとに 梅毒トレポネーマ抗体(TPHA)、STS(RPR)の定量検査の検査を行い、治癒の判断を行います。
| STS(RPR)陽性 梅毒 | 自動化定量法の RPR では治療前値の概ね 1/2、用手法である 2 倍系列希釈法の RPRでは、治療前値の 1/4 まで抗体価が低下したら治癒と判断 |
| STS(RPR)陰性早期梅毒 | RPR は治療効果の指標にならない。TP 抗体定量値が低下傾向にあれば治癒と判断。 |
治療開始後から4週ごとに確認をします。
治療をして効果不十分と判断される場合は、1 か月単位での投与期間の延長を検討するか、セロファースト(梅毒抗体価改善が不良)として専門家に相談が必要となります。
梅毒治療後の再検査は、治療完了後から1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後に行われます。1か月後の時点で治療完了と診断された後でも、確実な治癒確認のため治療完了後も細菌が完全に排除されたことを確認するために1年間は定期的な再検査で経過を見ていく必要があります。
治療費用
使用する抗生物質の種類、先発品やジェネリックか、院内処方か院外処方かによって費用が変わります。3割負担で千円~3千円程となります。
郵送検査、他院での検査(自費、保険問わず)で検査結果が陽性の場合、治療は保険で可能となりますが、本人の検査結果かどうかがわかる、氏名が明記された検査結果を持参の上受診が必要となります。治療効果の判定に必要となるため、梅毒トレポネーマ抗体(TPHA)、STS(RPR)の定量検査を行います。治療費用は上記の薬代と初診料、検査費用等で上記金額に加えて千~2千円程となります。
参照
日本性感染症学会 「梅毒診療の基本知識」の公開について https://jssti.jp/news_syphilis-medical_guide.html